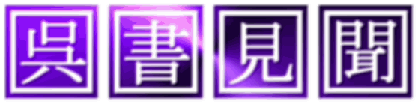【 許都襲撃はあくまで計画だった 】
- さて、沙羨の戦いが199年の12月8日に行われたのは間違えないと思われるので、孫策が江夏郡の攻略を断念したのは、200年当初の事だ。ここから孫策が死去するのが孫策伝注志林によると、200年4月4日。つまり、江夏から退却してほんの三ヶ月ほどで孫策は死の淵にあったのだ。その三ヶ月間に起きたことを検証してみる。
- 劉繇の死去
- 太史慈の豫章出向
- 華歆が孫策の上客となる
- 孫賁が豫章太守、孫輔が廬陵太守となる
- 孫賁、孫輔、周瑜、自称廬陵太守の僮芝を撃ち廬陵を占領する。
- 孫策、許都襲撃を計画する。
- 1の劉繇の死は199年中の出来事だと思われる。孫策が江夏から退却してから劉繇が死んだとしたら、あまりにタイミングが良すぎるだろう。おそらく孫策が劉勲・黄祖討伐を開始した時点ですでに死去していたはずである。でなければ劉繇が滞在していたはずの彭沢で孫賁・孫輔が劉勲を待ち伏せ攻撃をしたというのは奇妙な話になるし、また劉勲は劉繇が死去したからこそ、豫章を手に入れようとしたはずだ。
- そして太史慈の豫章出向であるが、これは周瑜伝8【 豫章制圧 】で述べたように黄祖討伐の後だ。おそらく、孫策が江夏の制圧を断念した直後、199年12月の事である。軍中の武将の中で劉繇旗下であり、また華歆と同郷であった太史慈を豫章の偵察に向かわせたのは、実に理にかなった選択だった。そして、太史慈は
- 華歆は旧劉繇の軍勢を取り込まなかった(華歆に野心なしと判断できる。)
- 僮芝や鄱陽の宗部などが反乱を起し豫章郡は安定していない(孫策に対抗できる状況ではない。)
- 話が逸れた。孫策は江夏から豫章に向かい、椒丘(南昌から数十里の所にある)に駐屯した。その時の様子は、華歆伝及び虞翻伝に詳しい。華歆伝によると、華歆は隠士のかぶる頭巾をかぶって孫策を奉迎し、孫策は上客に対する礼で接した、とある。なにげに見逃しがちだが、以外に重要な事が書かれている。隠士という事は隠居するという意味を指している。これはつまり、豫章太守の座を退くという意味だ。つまり、豫章太守の座に固執しないという意思表示であり、その意思表示があったから、孫策は上客として華歆を迎えた。だからこそ、その後、孫賁が豫章太守になれる訳である。また、虞翻伝注江表伝によると、虞翻は孫策が椒丘に駐屯した際、使者として華歆の元を訪れている。それを読むと、どうも豫章郡は食糧不足にあったようだ。華歆が旧劉繇の軍勢を取り込まなかったというのも、実はその辺に本当の理由があるのかもしれない。そういえば、孫策伝注江表伝にも、豫章郡でも廬江郡でも食料が不足していた様子が書かれている。
- さて、華歆が自ら豫章太守の座から降りたため、その後釜として孫賁が豫章太守となった。その後のタイムテーブルから考えて200年2月頃ではないかと思われる。孫賁はこれが初めての太守職である。以前に豫州刺史というのがあるが、これは実際に豫州を治めた訳ではない。つまり、これが実質的な初めての郡統治となった。といっても、郡を完全に支配した訳ではない。太史慈が報告したとおり、当時の豫章郡は反乱勢力が多く安定統治ができる状態ではなかったのである。
- どの程度の反乱勢力があったのかというと、まず上繚・海昏・鄱陽には宗帥(独立勢力のボス)がいた。上繚・海昏の宗民(独立勢力)については孫策伝に記述が見られ、鄱陽の独立勢力については太史慈の報告の中に記述が見られる。特に鄱陽の独立勢力は無視できる物ではなかったようで、呂範・韓当らが制圧に向かっている。同時に孫策は、統治が困難と思われる県に武官を配した。蒋欽が尉に任命された葛陽県、韓当が長に任命された楽安県は鄱陽方面にあり、周泰が長に任命された宣春県は海昏・上繚方面にある。これらの県はこうした独立勢力が闊歩する箇所であろう。 そしてもう一つの反乱勢力が廬陵の僮芝である。廬陵の僮芝が上繚・海昏・鄱陽らの独立勢力と一線を画していたのは、僮芝が廬陵太守を自称していたという点である。つまり上繚・海昏・鄱陽らの独立勢力は点在する独立勢力だったのに対し、廬陵の僮芝は豫章郡南部を支配する広域反乱勢力ではなかったかと思われる。よって孫策が孫賁を豫章太守に任命した目的は、孫賁の郡統治能力を期待してというより、僮芝撲滅作戦の一環であったと言える。だからこそ周瑜を豫章郡に配置したのだ。
- 僮芝については丹楊の人とあり、地元の人間でない事が分かる。という事は上繚・海昏・鄱陽らの宗帥とはやはり異なる。イメージとしては太史慈や祖郎らと同類に思える。広大な豫章郡では南部には統治が行き届かない事を見越して、廬陵太守を自称するという発想も太史慈が丹楊太守を自称したのと似ている。想像の翼を広げれば笮融同様に元の劉繇配下で、豫章郡の混乱に乗じて独立した勢力ではないかとも思える。
- さてこの時点で孫策は配下の将を相当数、豫章郡の配置しているのが分かる。まず豫章郡都の南昌に孫賁・孫輔及び周瑜。彼ら三名は廬陵の僮芝討伐のための人員だ。もう一つの反乱拠点である鄱陽には呂範を向かわせている。県レベルで見ると、蒋欽を葛陽県、韓当を楽安県、周泰を宣春県に配置している。彼らは反乱が起きやすい情勢不安定な県を押さえるための重しである。さらには太史慈が海昏・建昌など豫章西部六県の都尉として赴任したのもこの時期だ。太史慈の役割は劉表の侵入の阻止。こうして見ると丹楊に戻ったのは程普くらいだ。と言っても、程普は丹楊都尉として丹楊郡西部の山越を押さえる役割にあり、中央軍にいた訳ではない。これはどういう事かというと、200年2月~3月の段階で孫策軍は豫章・丹楊の反乱勢力の押さえのために分散しており、孫策の手元は手薄だったということを意味している。それが孫策暗殺直前の孫策軍の動向である。
- ここまで考えると不思議に思えてくる事があるが取りあえず先に行く。僮芝討伐要員として南昌に残った孫賁・孫輔・周瑜は廬陵に侵攻する機を伺う。そして僮芝が病にかかると一気に廬陵に侵攻し、周瑜は巴丘に軍を駐留させ、孫輔はそのまま廬陵を制圧した。この段階で孫輔は廬陵太守となった。孫策が死去するのが200年4月であり、孫賁の豫章太守赴任が早くても200年1月~2月である事を考えれば、廬陵制圧は200年3月の事と思われる。つまり僮芝討伐は孫策の死の直前の出来事だった。
- さて、不思議に思えてくる事とは、ずばり「よくここまで軍属が分散している状況で許昌襲撃など考えたものだ」という事である。孫賁は南昌、孫輔は廬陵、周瑜は巴丘。呂範は鄱陽、程普は石城。太史慈は建昌にいる。もし許昌を襲撃する気なら、彼らのうち少なくとも周瑜・程普・呂範は招集するはずだが、そういう気配がない。もし招集されていたのなら、孫策が死んだ時に彼らは呉にいたはずだが、周瑜や呂範は孫策死後に葬儀に駆けつけている。という事は、確かに孫策は許昌なり徐州なりに侵攻する事は考えていたかもしれないが、それはただの計画段階の事であり、軍を起こしていた訳ではないということだ。
- もう一度孫策の死についての諸説を整理してみる。陳寿の本文では、孫策は許昌を襲撃して皇帝を呉に迎えようと密かに計画していたが、計画を実行する前に殺されたとある。これは状況から考えて理にかなった文と言える。だが孫策伝注江表伝によると、孫策は西征の後、陳登の討伐に向かったとある。もしそうだとしたら周瑜も程普も呂範も招集せず、孫策ただ一人で徐州に侵攻しようとしたという事になり、どうも腑に落ちない。しかも江表伝によると、許貢の食客は当初、韓当の部下を名乗っており、当時、韓当は豫章郡楽安県の長であったことを考えれば、理屈に合わない文だ。つまり、状況から考えれば、やはり陳寿の本文の記述が最も信頼性が高いと思えるのである。イメージ的に、いかにも許都襲撃直前に孫策が殺されたような印象があるが、実際にはそんなことはない。許都襲撃はあくまでただの計画だったのである。そして江表伝のように徐州侵攻を描いた書が存在する事を考えれば、孫策はカモフラージュとして徐州侵攻を匂わせていた可能性は存在している。▲▼