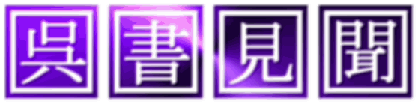【 荊州貸与とは何か? 】
- 魯粛の荊州貸与政策の持つ意味を考える前に、まず、覇業論を中心とする魯粛の考え方の整理、及び、当時の荊州事情の整理をしておく。
- と、その前に(汗)。まず、呉側の言う荊州貸与と言うのは、語弊が非常に多い。事実認識をしていくと、当時の呉は荊州全土を領有していた訳ではないからだ。呉が支配していたのは南郡と江夏の二郡である。しかも、その後の状況を見ても、江夏は貸与のまな板に挙がった事はない。つまり、荊州貸与ではなく南郡貸与である。具体的に言うと、周瑜の後を受けて江陵に駐屯した魯粛が江陵城を立ち退いた・・・という事件。それを呉書は一環して【荊州貸与】と言っているのであり、この認識がどこから来るか?と言うと・・・この荊州貸与という言い方が、魯粛伝に多く出現するという点が・・・・非常にポイントであると思う。
- まずは、魯粛の思考の整理から。
魯粛は、その覇業論の中で、【鼎立しつつ、長江流域を悉く支配する】事が【孫権を皇帝にする最短距離】と考えているのは間違えない。この鼎立と言う点が周瑜の天下二分の策との大きな相違点である。周瑜の天下二分の策は、鼎立する間でもなく長江流域を支配できるやり方だ。その代償として【孫権を皇帝にする】ことはできない。できるかもしれないが、最短距離ではない。 - 逆に【孫権を皇帝にする】ための最短距離を常に念頭に置いている魯粛からすると、兎に角、長江流域を曹操に支配される事が破綻の第一ポイントであり、曹操にさえ長江流域を支配されなければ良いと考えてる。これは、魯粛の覇業論にもその考え方が出てくるし、208年の荊州騒乱の際に魯粛が第三勢力として劉備を中心に荊州を纏めさせ、鼎立の一足にしようとした事からも明かである。
- つまり、何らかの形で鼎立しておく必要がある。これは別に第三勢力の事を尊重している訳ではなく、第三勢力に鼎立してもらった方が、後々、綻びを見て孫呉が支配しやすいから・・である。曹操に支配されてしまうと、挽回不可能なのだ。こうした点を見ていくと、魯粛の考え方は非常に長期的であり、おそらく、その中には曹操・劉備・孫権の中で、ダントツで孫権が若く、残された時間は圧倒的に多いという点がある。
- また、魯粛はこの段階で部隊を率いた事はなく、軍事面にはかなり疎かったと思われる。赤壁には参謀として参戦したのであるから、実質的に初めて軍を率いたのは、周瑜の後任として江陵に駐屯した時が最初である。少なくとも、自分が軍を率いて戦う事に自信をもっていたとは到底思えない。
- 次に、荊州事情である。当時、荊州では劉備勢力が成長し、孫呉に肩を並べつつあった。これは純然たる事実である。つまり、荊州の士大夫たちは続々と劉備に与しており、それは即ち、劉備が荊州での基盤を確実にしつつあったと言う事である。であるからこそ、周瑜は劉備を龍と称し擁立を促した。孫呉が江夏・江陵を支配できたのは、あくまで戦勝による物であり、長期的に見れば土着的基盤という意味で劉備勢力が有利であった。むしろ旧来の孫呉と劉表勢力との関係を考えれば、江夏・江陵に孫呉が駐屯している事の方が異常事態である。
- また、すでに劉備が荊州牧として各郡太守の任命を初めており、南郡にもそのメスが入れられている。劉備は張飛を宜都太守・関羽を襄陽太守として、そのまま長江北岸に駐屯させている。元々、宜都なんて郡は存在しておらず、劉備が南郡から分割したのである。関羽の襄陽太守にしても、実際に襄陽に駐屯できるはずがなく、関羽が駐屯できるとしたら南郡のいずれかしかあり得ない。つまり、この時点ですでに南郡における孫呉の権益が侵されつつあった。それも荊州牧としての正式な権限を行使しての事であるから、文句の言い様もない。
- この辺りが、魯粛の荊州貸与案の背景となる。とにかく、この男、一般常識論からはあり得ない発想をもって来る所が脅威である。危険ですらある。結論から言うと、あれほど重要ポイントであるとして重視していた江陵を、魯粛はあっさりと劉備に【貸与】した。それが荊州貸与案である。
- はっきり言っておくが、魯粛は純然たる天下三分論者ではない。純然たる天下三分論というのは、劉備勢力からしか出てこない。当たり前の話だ。わざわざ第三勢力の拡大を支援する第二勢力なんてあり得ないのである。そのあり得ない事を魯粛がやろうとしていたと考えるから、魯粛はお人好しだとか、孫呉のため成らざる事をやった人間だとか言われるのだ。魯粛の言う所の鼎立案は、曹操に取られるとまずいから、取りあえず第三勢力に長江流域に鼎立させるという事であり、最終的には併呑してしまう気である。ただし、その併呑のスパンは非常に長期的だ。【綻びを見ていつか併呑する】訳である。この考え方を見れば、不思議な事に、魯粛という男は、自分あるいは孫呉の実力という物を過大評価していない反面、第三勢力を操る事に関しては、過大評価ではないか?と思えるほど自信を持っている。私には理解すら難しい思考回路である。だが、歴史の出した結論から言うと、この魯粛の思考回路は正しかったと言わざるを得ない。
- 江陵貸与の持つ意味を考察していく。私は孫呉の言う荊州貸与は南郡・江陵貸与であると思っているので、以後は江陵貸与と書く。まず、はっきり言うと、この江陵貸与案は受動的理由と能動的理由の二種類が存在している。受動的理由とは、前述したように
- 荊州の基盤は劉備に有利である。
- 南郡の支配権すら、劉備によって侵されつつある。
- 一つには、この時期であるからこそ、南郡からの撤退を劉備への貸しとしてキープできるという点だ。呉側の資料が中心となるので、かなり差し引かねばならないが、どうも、その後の第一次呉・蜀対立を見ても、多少の負い目を蜀側がもっていたと思える節がある。劉備伝にすら【孫権は荊州を返して貰うつもりで・・・】という記述が出てくる。しかも劉備は【涼州を手に入れたら返す】なんて返答をしている。(これも劉備伝の記述。)蜀側の資料が不足しており、呉側の資料を元に陳寿が書いたとしても、すでに認識として【なんらかの貸与がされていた】と考えられていた訳である。
- つまり、江陵の貸与を大きな貸しであると認識させるには、まだ、劉備が基盤を作っている段階である、この時期に貸与するしか方法はない。なぜかと言えば、もしこのまま江陵を孫呉が支配したとしても、土着力という面で孫呉は基盤が弱く、下手をすれば統治に失敗して劉備が合法的に江陵に入るなんて事があり得ないとも限らない。それ以前に曹操に取られてしまっては意味を持たない。魯粛は自身の軍事能力を過信できる理由がなかった。おそらく魯粛が軍事能力的に信頼したのは周瑜一人であり、その周瑜がいない今、孫呉の軍事的実力は、赤壁時に比べ格段に落ちていると判断していたと思われる。
- 逆に今後も劉備陣営が急速に力を付けるだろう事も魯粛は予想可能である。そもそも魯粛は、赤壁段階から荊州を纏めるのは劉備しかいないと見ており、曹操を追い払えば、旧・劉表勢力は劉備に流れるだろう事は想像が付く。このまま事態を傍観すれば、いずれ荊州は名実共に劉備に全ての権益が移動するだろう・・・という危機感を最も強く抱いていたのが魯粛のはずだ。魯粛は、孫呉陣営の中で最も早く戦勝気分を頭から切り離し、冷静に現実を見ていたのである。
- また、この体制では、孫呉・劉備共に益州に食指を伸ばしづらい。劉備が益州に出る時には江陵に孫呉がいるというのが後顧の憂いになるし、孫呉の場合はもっとで、蜀に入ったとたん江陵を取られたら孤立するしかない。その状態で孫・劉共に蜀入のタイミングを失えば、曹操に蜀を先に取られる可能性が出てくる。つまり、この体制は発展性がないのだ。だとすれば、この体制を永久に続ける事は不可能である。
- すでに諸葛亮の隆中対策の中に荊・益を支配して・・という構想が出てくるので、益州攻略は劉備陣営の思考の中に入っていたはず。だからこそ、益州の出入り口を、宜都郡として孫呉の支配する南郡から切り離したのだ。その段階でどうぞ使いなさいとばかりに江陵から魯粛が立ち退くのであるから、純軍事的にも外交的にもかなり安心した状態で蜀入できる。後は、江陵に曹操が来る危険性だが、これは212年に曹操が濡須に向かった事で解消される。これを待っていたかのように劉備は行動を開始する訳だ。孫権伝に、劉備が蜀入すると、「このペテン師めが・・・」と怒ったとあるが、これは別に蜀入を孫権が予想してなかったという訳ではあるまい。あくまでも、劉備が「劉璋は同族だから・・・」なんて小細工を言った事、あるいは呉が濡須で激戦を繰り広げている間に蜀入した事に対する皮肉である。曹操の濡須方面への侵攻という問題があるにしても、劉備が蜀制圧が完了する214年までの長い間、孫呉はそれをただ傍観していた訳であるから、ある程度の予定調和は存在している。
- つまり、江陵貸与の持つ政治的・軍事的効果は・・・・
- 周瑜死後の孫呉の軍事的実力に見合った形で戦線を縮小できる。(揚州方面のみに専念できる。)
- 一方で実力をつけてきた劉備に、その実力に見合う形で荊州方面の防衛を一任させる。
- 土着基盤のない江陵から、孫呉の権益を保留した状態で撤退できる。
- 劉備に貸しを作る事で後々の外交カードと成りうる。
- 劉備の蜀入を促す事で、曹操より先に長江流域に鼎立が完成する。
- 以上のような観点から、魯粛は大事な大事な江陵をあっさりと劉備に【貸与】したのである。語弊はあるが、190年代後半の袁術と孫策の関係に状況的には似ている部分がある。丹楊は袁術と孫策の共同軍(実質、袁術軍)で取ったとしよう。これが江陵に当たる。その後、呉・会稽は孫策が自力で取った。これが劉備の南部四郡に当たる。結局、袁術は丹楊(江陵)の権益に執着したのでそれすら失った。魯粛が袁術の立場であると仮定すると、魯粛は丹楊(江陵)から意図的に立ち退いて、孫策(劉備)に貸しを作った事になる。実に辛辣極まりなく、逆にその後の対応次第で危険性すら孕む、ギリギリの策である。 ▲▼