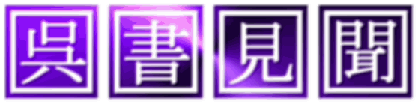【 210年の真実 】
- 実は、京城会見が209年の事なのか?210年の事なのか?は断言できない。劉備と孫権の二つの本紀のうち、孫権伝は京城会見の事を一切無視し、劉備伝はその時期の特定が出来ないからだ。だが209年のタイムテーブルを並べてみると、翌年の210年の事と見た方が無理がない。210年の本紀の記述を追う。
【孫権伝本文】
- 210年、長沙郡を分割して漢昌郡を作り、魯粛をその太守とし陸口に駐屯させた。
【劉備伝本文】
- 恐らく210年、孫権は劉備をだんだん畏れるようになり、妹を与え友好関係を深めた。
- 恐らく210年、劉備は京城に出向いて孫権と会談し、極めて親密な間柄となった。
- 恐らく210年、孫権は使者を遣わして蜀を共同して取ろうと申し出た。
- 恐らく210年、ある者は「呉は荊州を越えて蜀を支配するのは不可能であるから、承知せよ。」と言ったが、殷観は「もし呉の先駆けとなり、進んでは蜀を落とせず、引いては呉につけ込まれるような事があれば、好機を失うので、ここは賛成する一方で、我々は諸郡を支配したばかりだから、まだ行動は取れないと説明するのが良い。呉は我が領土を越えて蜀を取る事はしないでしょう。」と言った。劉備がそれに従った所、孫権は計画を中止した。
【劉備伝注献帝春秋】
- 恐らく210年、孫権は、孫瑜に水軍を指揮させ夏口に駐屯させた。劉備は軍の通過を認めず、関羽を江陵、張飛を秭帰に駐屯させた。孫権は孫瑜を召還した。
- 京城会見、あるいはそれに類する外交については、劉備伝の方が詳細に記し、孫権伝の方はそれを無視するという、珍しい構図となっている。大体の場合は、呉書が詳しく蜀書は簡潔で時期が明確でない事が多い。つまり京城会見の事は、劉備に取っては重要だが、孫権に取っては重要ではないと見て良いだろう。
- また、この年は曹操伝には呉・蜀に関連する記述はなく、求賢令と銅雀台の事が書かれているだけだ。つまり、210年は戦争状態になく、呉・蜀は外圧を畏れる必要が薄れている。また孫権伝にある魯粛を陸口に駐屯させたというのは、周瑜死後の事である。つまり、210年は京城会見で始まり、続いて周瑜の死去、魯粛の陸口移転と続いている。最後の蜀攻略を巡っての呉・蜀の軍事緊張が書かれた献帝春秋の注は、周瑜死後の事であるのは特定できる。孫瑜の事しか出てこないからである。非常に面白い事が書かれて採用したい異説なのだが、注である事と献帝春秋の引用であるという点で、信憑性で?が付く。三国志は裴松之の注があるから面白いのだが、ただ事実認識のみを確認したい場合は、その多説ある注の存在が、輪郭をぼやかしてしまう場合が多い。よって、今回は注で挿入された異説については一切無視し、陳寿の本文の持つ信憑性のみを事実として認識する。それに京城で起きたと思われる列伝の記述を合わせていく。
【周瑜伝本文】
- 劉備が京城にやってくると、周瑜は劉備を呉に留め、美女・愛玩物・宮殿を与え、関・張は将として用い、劉備に基盤を与えては成らぬと説いた。
- また、周瑜は京城にやってきて、蜀を奪う計画を進言した。孫権はこれに同意した。
- 劉備が京城から帰還する時に送別会を開いたが、その時劉備は周瑜はいつまでも人の下にいる人材ではないと言った。
【魯粛伝本文】
- 劉備が京城に来て、荊州の都督になりたいと申し出た時、魯粛だけが荊州を劉備に貸し与え、協力して曹操を退けるのが良いと進言した。
- 曹操は孫権が土地を割いて劉備に貸し与えたと聞くと、持っていた筆を取り落とした。
- 周瑜と甘寧は蜀を奪うように進言した。孫権がそのことについて劉備に相談すると、攻め取る気はないと答えた。
【呂範伝本文】
- 劉備が京城に来ると、呂範はこのまま劉備を呉に留めよと進言した。
- 1の周瑜の進言については、周瑜伝【天下二分の策の裏側】で述べたように、これは劉備擁立を促した物であると私は思う。魯粛の覇業論と戦略論的には同類の策だが、魯粛の覇業論と何が違うか?というと、
- 漢王朝の意義を無視していない。(大義名分論として漢の権威を利用しようとした。魯粛はその点は一切無視している。江東有数の名家の生まれである周瑜と、豪族ではあっても名家ではない魯粛の思考背景の差と言って良い。)
- 一気に二分を実現しようとしている。(魯粛案は、三分状態(鼎立)状態から、時を見て二分に移行する策。これは周瑜と魯粛の軍事戦略理論の差だろう。魯粛は軍事は門外漢なので、勢力的な強さしか見ていない。よって孫呉の実力を過大評価せず、無理のない形での二分への移行を根本とした。周瑜の方は軍事経験と状況分析から一気に蜀を制圧可能であると考えた。)
- 周瑜が劉備が京城に来ている時に進言したのは、この劉備擁立だけであり、周瑜の蜀制圧計画の進言は劉備帰還後の事のように思える。なぜかと言うと、周瑜伝の記述からしてこの二つの進言を分けて書いており、またそれを受けた形の孫権の劉備への共同での蜀制圧提案は、使者を介してである。つまり、劉備が京城から帰還した後の事だ。また、劉備が京城から帰るときには、まだ周瑜は生きていた。
- 同時に、劉備が京城に来たとき、魯粛は劉備に(天子になったつもり論で言う所の)荊州を貸し与えよ、と進言した。また、劉備は荊州の都督になるためにやってきたとある。だが、この場合の荊州貸与とか都督とかは呉側の都合の良い書き方であり、荊州を貸すという言い方が妥当であるとは思いがたい。だが、一つ先入観を捨ててみると見えてくる事がある。別に京城会見の時に、劉備への(呉側の言う所の)荊州貸与が決まった訳ではないのだ。魯粛の進言に対する孫権の反応は本文には一切記されてない。
- またまた同時に、劉備が京城に来たとき、呂範は劉備を呉に留めよ、と進言した。これが周瑜と同様の進言内容であるのか?あるいは、劉備を捕捉し荊州を武力制圧せよ、という意味なのか?は計りかねる。確かなのは、周瑜と呂範は二人そろって進言したのではなく、別々に進言したという事だ。また、これに対しての孫権の反応も本文は沈黙している。
- これが、事実として認識しうる部分である。これを見て浮かび上がってくる事は、京城会見では、劉備に対する処遇を巡って、周瑜・魯粛・呂範という赤壁の功労者が揃って、別々の進言をしたという事、そしてそれに対する孫権の反応は、本文には一切書かれていないという事だ。つまり、これこそが真実であり、実は京城会見では孫権は何も決めていない。何も決めていないからこそ、孫権伝は沈黙し、劉備伝に親密な関係になった・・・・とあるのだ。京城会見前後の外交について劉備伝が多弁なのは、赤壁段階では後方で見ているしかなかった劉備勢力が、孫権と肩を並べ畏れられる勢力にまで成長したという証明であるからだ。
- もし、京城会見の段階で、孫権が魯粛の進言を聞き入れ、(呉側の言う所の)荊州貸与を決めたのなら、周瑜がその後で、蜀侵攻計画を進言するはずがない。荊州が劉備に譲渡?された状態で蜀制圧など不可能だからだ。また、周瑜や呂範の進言も無視或いは保留されたのは、劉備が普通に帰還したのを見れば分かる。よく考えれば、当時の孫呉の国家事情から言って、このように家臣団の意見が分かれた場合に、孫権が主導性を発揮できるはずがないのである。つまり、柴桑会議同様、結論を保留していた。
- で、最終的に孫権がなんらかの行動を示したのは、京城会見の後である。これも、本文だけを見れば、結局、周瑜の策を孫権が起用したことが分かる。孫権は劉備に対して共同で蜀を取ろうと提案しているからだ。これは明らかに、周瑜の蜀制圧論を受けての事であり、つまり、劉備を擁立する事については保留した物の【連立政権を維持する】事については賛同した。連立維持でなくては、共同での蜀制圧なぞ不可能である。劉備はこの提案を受け、その微妙な立場から殷観の案を採用し、それに賛同しつつも時期尚早とした。つまりはぐらかした。殷観の言うように、この外交が失敗した時点で、周瑜の蜀制圧論は破綻している。やはり、劉備擁立まで行かなくては連立維持はできなかったのだ。それくらい、劉備勢力は急速に力をつけていたのである。
- この直後に周瑜は病身となり、巴丘で病死する。この段階に至って、呉側に遠征軍を指揮できる将帥が居なくなる。そして劉備が共同での蜀制圧を拒否した時点で、【連立維持が不可能】である事が明白となり、魯粛の(呉側の言う所の)荊州貸与案が浮上した。実の所、周瑜の天下二分の策は魯粛の覇業論の精神に沿って計画された案であり、二人の意見が対立する要素はない。対立する要素があるのは、【劉備擁立】である。これは、周瑜が名家の生まれであり、漢王朝の権威から脱却する事ができなかったのに対し、そうした価値観から自由な魯粛は、孫権を帝王とする事に情熱を注いでいるという点からくる対立要素である。そもそも魯粛は劉備を擁立する意味について無頓着だったという事ではないか?と思う。いずれにしても、周瑜という軍事戦略能力に優れた将帥を失った時点で、孫呉の戦略は外交戦略中心に成らざるを得なかった。つまり、ここから呂蒙という将帥が現れるまでの間、孫呉は魯粛の外交戦略をかなめとして行動していく事になる。▲▼
- (注)魯粛伝に、病気が重くなった周瑜が孫権に「私の後任は魯粛が良いです。」と言ったというエピソードが載っている。このエピソードのおかけで、「周瑜→魯粛」と、呉の実質的指導者がリレーされたかのような印象を受ける。そう思っている人も多いはずである。
だが、実際に周瑜の後をうけ、南郡太守になったのは程普である。当たり前の話であり、軍事経験のない魯粛を、軍人・周瑜の後釜に据えたりしない。後任は周瑜に次ぐ実績を持つ軍人・程普である。
では魯粛は周瑜の何を引き継いだのか?それは「周瑜の部曲(私兵)」と「周瑜の奉邑」である。つまり、本来、世襲されると思われる部分を魯粛が「世襲」している。問題はなぜそんなことになっているのか?である。
周瑜の長子である周循は「若くして死去」とあり、おそらく周瑜が死去する前に死去している。つまり、長子・周循が健在であるならば、周瑜の部曲と奉邑は周循が引き継ぐのが普通だが、周瑜死去の時点ですでに周循は死去しており、次子は周胤はまだ成人していなかったのではないか?と思われる。よって、世襲が認められず、周瑜の部曲と奉邑は魯粛に引き継がれた。つまり、魯粛が周瑜から引き継いだ部分というのは、周家の存亡に関わるデリケートな部分であり、それを周瑜が「私の兵力と土地は息子じゃなく魯粛さんにあげてね。」なんて言うはずがない。これは周瑜の急死を受けて、国益を鑑みて孫権が決定したことであるはずである。赤壁の勝利により、発言力が増していた魯粛に実質的な勢力背景をつけさせるための措置である。
- (注)魯粛伝に、病気が重くなった周瑜が孫権に「私の後任は魯粛が良いです。」と言ったというエピソードが載っている。このエピソードのおかけで、「周瑜→魯粛」と、呉の実質的指導者がリレーされたかのような印象を受ける。そう思っている人も多いはずである。