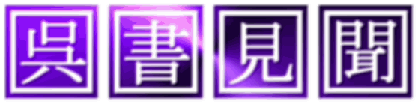【 石亭の戦い 】
- 226年7月,魏の文帝こと,曹丕が死去する。孫権はこれを魏を攻める好機と見る。荊州に駐屯する陸遜は魏に隙はないと報告するが,孫権はそんなことはないだろうと考え,江夏から石陽を攻撃する。石陽は丁度夏口から北上した位置にあり,おそらく孫権は防備の固い襄陽・合肥を回避してその中間地点にあたる石陽を攻撃したと考えられる。この時,石陽を守備していたのは文聘である。文聘はよく城を守って隙を見せなかった。やはり陸遜の報告のように曹丕から曹叡に皇帝が変わっても国境守備軍に隙はなかったのだ。結局,孫権は石陽に長居する事無く,二十日ほど包囲するとさっさと退却してしまった。『魏略』には,文聘が空城の策を用いた事になっているが,これはどうも信憑性が薄い。どうもこの頃になると魏・呉・蜀それぞれで防御ラインが強化され,攻撃する方は守備側より相当の戦力差がなければ攻撃は成功しない状態になっていたと考えられる。三国の鼎立により戦局は膠着していったのである。
- (注)よく、蜀は本気で魏を倒そうとしたが、呉は消極的で地方政権に甘んじた・・という評価を耳にすることがある。しかし、孫権存命期(呉王就任以降)の外征(対魏戦のみ)の数は、諸葛亮の北伐(5回)をはるかに超え大小合わせると10回に及ぶ。特に曹丕死去時は「やるならここしかない」という決意が孫権(石陽侵攻・石亭の戦い)・諸葛亮(出師の表)双方に見られる。
- こうなって来ると,単独の力攻めでは強大な魏を倒すのは難しい。そこで228年頃から呉・蜀による共同作戦が見られるようになる。第一次呉蜀同盟では,残念ながら呉と蜀が共同して魏に当たるということはなかった。唯一共同作戦だった赤壁の戦いは,そうするしかなかったという感が強い。その後は魏と呉が激突している間に劉備は巴蜀に勢力を伸ばし,漢中で魏と蜀が対立すると,呉蜀間で荊州問題が頭をもたげて来るという,実にチグハグな同盟であった。これはトップである孫権と劉備間に互いに利用してやろうという考えがあったためである。しかし孔明の思考・行動は一貫して反魏・反曹であり,孫権としても信頼の置ける同盟相手だったのだろう。
- 蜀では227年に孔明が歴史に残る名文,『出師の表』を著して練りに練った第一次北伐作戦を開始,228年春には街亭の戦いが行われている。その頃,呉でも準備を重ねた曹休誘い込み作戦が計画されていた。残念なのはこの二国の作戦が,同時進行ではなく,約半年のタイムラグがある点だ。しかし作戦の効果的発動時期という事と,遠く本拠の離れた呉と蜀では完全な一致行動は難しいという点を考えると仕方ない事なのかもしれない。
- その頃,呉では国境守備隊の部将の数名が呉を離反して,魏に付くという事件が起きていた。韓当の息子・韓綜と翟丹の魏への投降事件である。これは両名が失策の責任を取らされるのを恐れて魏に投降したというのが真相らしく,その直後に孫権は『今後,部将の失策は三つあって始めてその責任を問う事にする。』と令を下している。孫権はこの投降事件を逆手に取る。周魴(しゅうほう)に偽の投降をさせて,魏軍の曹休を誘い込み叩こうという物である。周魴は孫権に対して剃髪して罪を謝罪するという芝居までやっており,その情報を得ていた曹休はこの投降を全く信じてしまっていたのである。
- ただし,孫権の側にも誤算があったと思われる。曹休が皖城に攻めてきたのは予想の範疇だったのだが,街亭において孔明軍が手痛い敗北を喫して退却したため,蜀方面に出向いていた張郃らの軍まで呉に向かってきたのである。結局,魏の進軍は皖城・東関(濡須方面)と江陵からの三方面進入という結構大規模なものになっていた。ただ幸運だったのは,季節は既に冬になっており,江陵に進軍した司馬懿・張郃は部隊戦を行っただけで,凍った長江を渡れずに引き返し,また東関に向かっていた賈逵軍は曹休が罠にはまったらしい事を察知しており,曹休の救出に追われたのである。結局,戦いの焦点は孫権の目論み通り,罠にはまった曹休軍のみとなった。そうとは知らない曹休は意気揚揚と皖城を落とさんとやってくる。これに対して孫権は陸遜を大都督に任命,陸遜は石亭で三方向から曹休軍を攻撃,曹休は寸での所で賈逵に助けられ逃亡する。曹休はこの戦いの後,背中に悪性の腫瘍が出来て,まもなく病死している。
- しかし,蜀の第一次北伐の結果と孫権の石亭の戦いの順序が逆であったら??と考えてしまう。石亭で孫権軍が勝ち,それを受けて孔明が北伐を開始する形が一番理想的ではあった。このパターンが一番,魏軍の動揺が誘えるし,張郃も街亭に出向けなかったかもしれない。しかし所詮はIf・・・の話である。指揮系統の異なる二国が完全に理想的に軍を動かすことなど無理なのであろう。結局天下三分の策の欠点はそこにあるような気がする。 ▲▼