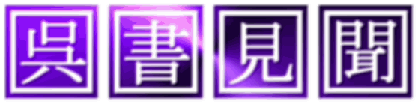【 柴桑会議 】
- 魯粛と孔明が孫権の説得のために,江東に出立した頃,孫権は柴桑に軍を進めていた。江表伝によると、そこに曹操から降服を勧める書状が届く。『南方の朝敵たちを倒そうと軍を起したら,荊州の劉琮は一戦も交えず降服しましたよ。これから孫権将軍と会って,江東で狩りなどしてみたいものですな。』曹操らしい,極めて陰を含んだ言い回しだが,直接的でないだけに,なおさら曹操の自信と脅威を思い知らされる内容である。ここで孫権は群臣を集めて曹操に対してどう対処するか朝議を行う。そこにタイミングの悪いことに,独断先行で劉備と同盟関係を約束してしまった魯粛一行が戻ってくる。この独断先行は張昭らの激怒を買い,柴桑会議では魯粛には発言権はなかったのである。柴桑会議は,孔明らの同盟申し込みの使者を受けて,劉備と同盟すべきか否かという会議ではなく,あくまで孫権一門が曹操に対してどう対処するかという会議という性格を帯びていたのである。
- では群臣たちの反応ばどうだったか?ほとんど満場一致で降服すべきだったのである。これは劉琮が曹操に下った時とほぼ同じ反応である。状況を考えれば降服するのが最も理論的であった。まず曹操軍の数が尋常ではない。元々中原から曹操が連れてきた軍が大軍だったのに加え,劉琮が一戦も交えずに降服したため,その数は膨れ上がっている。さらに曹操は荊州の水軍をその手中に収めたため,長江を頼みとする水上戦も有利とは言えない。勢いから言っても,荊州を手に入れ,士気の上がる曹操軍に比べ,呉の方はいまいち一丸とは言えない。さらに大義名分という意味でも,皇帝の後ろ盾のある曹操に対して,北方から参入してきた清流派の士人たちは,いまいち本気で対峙する気にはなれなかったのであろう。対峙すれば朝敵である。この朝敵という言葉に清流派の人材たちは,決定的に拒否反応を示したはずである。付け加えて,例え降服したとしても,劉琮とその配下のその後の処遇を見ても,決して降服したら明日はないというわけでもなかったのである。
- それに対して反対論を述べる立場にあった魯粛には,独断先行のつけで発言権がない。会議の隅でじっとしているしかなかったのである。そこで魯粛は孫権が『ちょっとトイレ。』と言って会議場を抜け出した一瞬を狙って孫権に近寄る。孫権と魯粛はトイレで会話をするはめになってしまった^^;。孫権は魯粛の手をとって(手は洗ったのか?^^;)『何か言いたいことあるんだろ?』と言う。孫権としても降服論ばかりでどうも納得できなかったのであろう。孫権としても魯粛の意見は聞いておきたかった。魯粛は孫権に対して『あいつらは自己の保身しか考えてないっすよ。だって私や張昭さんは名声があるから曹操に下ってもそれなりに重宝されるだろうけど,孫権さまは家柄は良くない上に,一度降服した君主を曹操が重宝して使うわけがないですよ。降服したらダメですよ。』と言う。これは半ば脅迫に近い。魯粛としても切羽詰まっていたのである。それにしても孫権の立場の弱さは目を覆うばかりである。孫権には江東を切り開いた実績がない。江東を切り開いたのは孫策であり,それを助けた群臣たちであった。その意味では魯粛も弱い。だから孫権と魯粛が抗戦の意思を示しても,それに理論的裏付けがなければどうしようもなかった。抗戦して勝てるという裏付けが。それを示してくれる実績のある人が。いや,一人いるではないか。孫策の無二の友であり,江東制圧の立役者・周瑜が。孫権と魯粛は周瑜を呼び寄せる。柴桑会議の第二幕が上がった。
- 柴桑会議が行われていた頃,周瑜は柴桑会議には出席しておらず,鄱陽湖で水軍の訓練を行っていた。おそらく周瑜は,鄱陽湖で曹操軍の動向とそれを叩くための戦略を練っていた。しかし孫権から柴桑に来てくれという書状が届き,『俺がいかなゃー,話にならんか。』と言う訳で柴桑に赴く。この周瑜の見解が柴桑会議の去就を定める重要な分岐点となっていた。
- 周瑜は柴桑に出向くと,勝機ありという理論を展開したのである。周瑜の論点は純粋に軍事的側面から見ての論理であった。まず周瑜は曹操軍の内情を調べ上げ,曹操軍の実態は,曹操が宣伝しているような80万という数ではなく,20数万人。しかも慣れない風土のために疫病が発生しているという事実をつかみ,さらに曹操軍のほとんどは騎馬隊で水上戦ならこちらが有利という理論を展開する。降服を主張している清流派の人物たちはほとんどが文官であり,戦争の勝機云々にはうとい。具体的な勝機を突き付ける事が最も効果的であったのである。周瑜の言を受けて,程普・呂範といった,一定の発言権を持つはずの軍人たちも勢いづいたと思われる。柴桑会議は,初めとはまた違った方向に行きつつあった。
- (注)よく柴桑会議に、呉の重要人物である周瑜が初めのうちは出席していないのはなぜか?という疑問が上がる事がある。だが、地図を見て見れば、鄱陽湖と柴桑は大変近く、いつでも周瑜は出席できる状態であったのは確かであろう。という事は、魯粛・諸葛亮が到着した時点で周瑜は鄱陽湖にいた。文官たちは柴桑にいたわけだが、事が事なので周瑜らの到着を待たずに会議を開始、同時に周瑜らにも柴桑に戻るように指令が飛ぶ。柴桑に戻るように指示された周瑜が到着した頃には丁度、魯粛らが苦戦している最中であった・・・と考えると、自然ではある。つまり、周瑜は途中から呼ばれたのではなく、到着が遅れただけなのかも知れない。また、そう考えると、柴桑会議の前半は降伏論が圧倒的で、後半になって抗戦論が出た理由もなんとなく掴める。鄱陽湖で軍事訓練を行ってたのが周瑜だけであるはずがないからである。軍部の下っ端には発言権がないのは当然だが、周瑜・呂範・程普らは、功績も大であり、柴桑会議で発言権がないはずがない。しかし、柴桑会議当初は軍部は訓練に出ていたのでは?というわけで周瑜同様、後から柴桑に駆けつけてきたので、柴桑会議後半には、抗戦論が増加しつつあったのかもしれない。
- 孫権はこれを受け,柴桑会議で始めて,君主としての主導性を発揮する。勝機がある以上,逆賊曹操を叩くべきであり,降服なぞもっての外であると主張。『これ以降,降服を唱える者はこの机同様に斬る!!』と一喝し,目の前の机を一刀両断にする。最後の最後になって,孫堅・孫策と続く武門の家系としての血がたぎったのである。
-
-徹底抗戦-
-