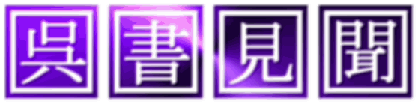【 遼東情勢への介入 】
- 孫権は229年の5月,張剛(ちょうごう)と管篤(かんとく)を使者として遼東に向かわせている。遼東では228年に公孫淵(こうそんえん)が公孫恭(こうそんきょう)を追いやって当主となっていた。公孫一族が遼東に覇を唱えた歴史は古い。190年には,公孫度(こうそんたく)は『漢王朝の命運はつきており,自分が帝位につく時が来た。』と言って,遼東の王を自称している。その後,後を継いだ公孫康(こうそんこう)は,曹操への帰順を示すが,公孫康が死んで性的不能者である公孫恭が後を継ぐと,野心に燃える公孫淵がその位を奪い取った訳である。この様に,魏と言えど遼東までは支配は及ばず,遼東での公孫一族による自立の歴史は古いのである。三国時代をさして,本当は三国鼎立ではなく,曹・孫・劉に公孫一族を加えて四国鼎立というべきだという意見すらある。
- 始めの呉と公孫淵の交流は,遼東の馬と南方の珍品の交換という,交易ルートからスタートしたものと思われる。232年には,周賀(しゅうが)と裴潜(はいせん)を遼東に送って馬と絹などの交換を行っている。また,公孫淵は返礼の使者として宿舒(しゅくじょ)と孫綜(そんそう)を呉に送った。公孫淵の思惑としては,できるなら遼東の王として自立したいという野望がある。そのために呉が魏に対抗できるなら,盟主として仰いで,魏に対抗しようという気持ちを持っていたと思われる。
- しかし,この公孫淵の考えは,その後,一変する事になる。おそらく宿舒と孫綜が返礼の使者として呉に出向いたのは,呉が魏に対抗できる国力を有しているかどうかという偵察の意味もあったはずである。しかし宿舒と孫綜は結局,呉は頼るにしかずという判断を下したのではないだろうか。実際の所,呉も蜀も天然の要害を頼りになんとか鼎立しているというのが実状であった。公孫淵が魏に背いたとしても,遠すぎる上に国力で魏に劣る呉の援護は期待できない,そういう事だったのかもしれない。
- 孫権は233年,宿舒・孫綜が帰国するのに随行させて,張弥(ちょうぴ)・許晏(きょあん)・賀達(がたつ)を使者として派遣,公孫越を燕王とした。しかし,襄平に出向いた張弥と許晏は公孫淵に切られ,魏に首を送られてしまう。面目を潰された孫権は激怒して,自ら公孫淵の討伐に出ようとするが,顧雍・張紹・薛綜らがこぞって諫めたために思いとどまっている。また,孫権の遼東派遣隊の一員であった,秦旦(しんたん)・張羣(ちょうぐん)・杜徳(ととく)・黄彊(こうきょう)らは遼東からさらに北方に逃亡し,高句麗王・位宮(いきゅう)と連絡を取るが,結局,位宮も236年にやって来た,呉の使者である胡衛(こえい)を切り,首を魏に送っている。
- 公孫淵に関しては,さらに続きがある。公孫淵は魏への臣従の姿勢を見せたものの,鮮卑族を味方につけ,魏に反乱,燕王を名乗る。238年には,司馬懿が遼東への遠征を敢行,公孫淵は再び呉に援助を求める。しかし,孫権にすでに本気で公孫淵を助ける気持ちもあるはずもなく,様子見に徹する。結局,公孫淵は司馬懿に破れ,その首は洛陽に届けられる事になる。こうして,孫権の遼東情勢への介入は大失敗に終わり,ただ孫権のメンツが潰されただけとなった。
- さて,同盟というのは,二種類ある。一つは近隣同盟,もう一つは遠方同盟である。日本では前者には織田・徳川同盟があるだろう。領地が隣接している者同士が互いに異なる進行方向を持つ場合に有効であり,三国時代では呉・蜀同盟がそれに当たる。後者である遠方との同盟は,日本では足利義昭主導による信長包囲網などがあるだろう。巨大な一つの勢力に対して,勢力が劣る者同士が協力して対抗する場合に有効であり,孫権が遼東の公孫淵や高句麗の位宮と盟を結ぼうとしたのには,魏を北方から威圧する勢力として期待していたという点があるはずである。ただし,問題点がいくつかあった。まずは孫権が公孫淵の人物像をよく調べないまま,盟を結ぼうとした点である。公孫淵はその後の動きを見ても盟を結ぶには信用に足りない人物である。次に遼東の勢力が魏に対抗しうると考えた点。実際には,ひとたび魏が遠征を起こせば,公孫淵は敗れてしまうのであり,高句麗が中華を脅かす勢力になるのは,もっと後の事になる。三国時代にはまだまだ北方の勢力は力不足だったのである。さらに,共に協力体制を取るには呉と遼東ではあまりにも遠すぎた。いざ事が起きてから行動に移れるまでに相当なタイムラグが出る。だから,公孫淵も最終的には呉ではなく,鮮卑族との同盟で燕王を名乗った。
- こう考えると,孫権の遼東情勢への介入は,方針として魏の驚異となる可能性はあったものの,その可能性は限りなく低かった。しかし呉にとしても蜀にしても,その限りなく低い可能性に賭けざるを得なかった。結局,それが孔明の死を賭けた北伐であり,孫権の無謀・無策に見える遼東情勢への介入であるとも言えると思えるのである。 ▲▼